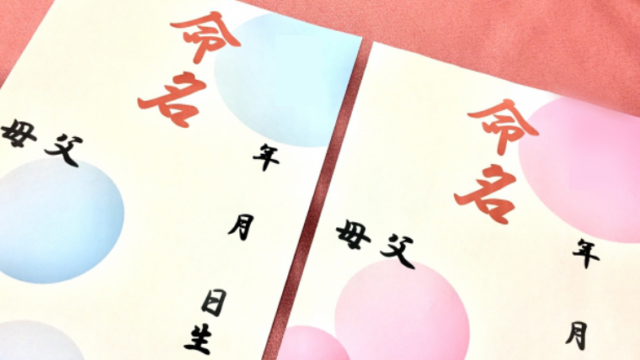旧暦で取り入れられた二十四節気あるいは雑節は、季節の目安や年中行事という形で、日々の生活に根づいています。
二十四節気の読み方は「にじゅうしせっき」と読みます。
- 二十四節気とは季節の節目を表すもの
- 二十四節気
- 1月:小寒 しょうかん 1月5日頃
- 1月:大寒 だいかん 1月20日頃
- 2月:立春 りっしゅん 2月4日頃
- 2月:雨水 うすい 2月19日頃
- 3月:啓蟄 けいちつ 3月5日頃
- 3月:春分 しゅんぶん 3月21日頃
- 4月:清明 せいめい 4月5日頃
- 4月:穀雨 こくう 4月20日頃
- 5月:立夏 りっか 5月6日頃
- 5月:小満 しょうまん 5月21日頃
- 6月:芒種 ぼうしゅ 6月6日頃
- 6月:夏至 げし 6月21日頃
- 7月:小暑 しょうしょ 7月7日頃
- 7月:大暑 たいしょ 7月23日頃
- 8月:立秋 りっしゅう 8月7日頃
- 8月:処暑 しょしょ 8月23日頃
- 9月:白露 はくろ 9月8日頃
- 9月:秋分 しゅうぶん 9月23日頃
- 10月:寒露 かんろ 10月8日頃
- 10月:霜降 そうこう 10月23日頃
- 11月:立冬 りっとう 11月7日頃
- 11月:小雪 しょうせつ 11月22日頃
- 12月:大雪 たいせつ 12月7日頃
- 12月:冬至 とうじ 12月22日頃
- 五節句と雑節
二十四節気とは季節の節目を表すもの
現在の暦ということは明治6年に採用されたものになります。それより前の日本では長期に亘って「月日」を月の満ち欠けをひと月とする太陽暦で、「季節」を太陽の動きを根拠とした太陽暦で示す旧暦を用いてきたのです。旧暦においては、四季に加えて、1年を24等分した二十四節気(にじゅうしせっき)、72等分した七十二候があって、季節の変化をこまやかに意味することで農作業などの指標としていたわけです。
このうち二十四節気は、現在でも季節の節目になるとよく用いられることから、ぜひとも覚えておくことをおすすめします。
二十四節気
1年を24等分した二十四節気を1月から12月まで順に紹介します。
1月:小寒 しょうかん 1月5日頃
 本格的に寒くなる少し手前。小寒は「寒の入り」ともいわれ、立春までの約1ヵ月が「寒の内」です。
本格的に寒くなる少し手前。小寒は「寒の入り」ともいわれ、立春までの約1ヵ月が「寒の内」です。
2020年の小寒は1月6日月曜日となります
1月:大寒 だいかん 1月20日頃
 二十四節気最後の節で、1年でもっとも寒い時期です。一方で少しずつ日が長くなり、春に近づいてきます。
二十四節気最後の節で、1年でもっとも寒い時期です。一方で少しずつ日が長くなり、春に近づいてきます。

2020年の大寒は1月20日月曜日となります
2月:立春 りっしゅん 2月4日頃
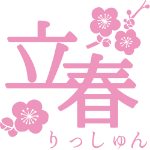 次第に春めいてくる頃となります。二十四節気で最初の節となります。八十八夜や二百十日などは立春から数えます。
次第に春めいてくる頃となります。二十四節気で最初の節となります。八十八夜や二百十日などは立春から数えます。
2020年の立春は2月4日火曜日となります
2月:雨水 うすい 2月19日頃
 まだ雪は残るものの、氷は解け、雨が雪に変わる頃で、農耕の準備をはじめる目安となります。
まだ雪は残るものの、氷は解け、雨が雪に変わる頃で、農耕の準備をはじめる目安となります。

2020年の雨水は2月19日水曜日となります
3月:啓蟄 けいちつ 3月5日頃
 冬眠していた虫たちが、春の気配を感じて地面に現れはじめる頃となります。日ごとに陽気が良くなります。
冬眠していた虫たちが、春の気配を感じて地面に現れはじめる頃となります。日ごとに陽気が良くなります。
2020年の啓蟄は3月5日木曜日となります
3月:春分 しゅんぶん 3月21日頃
 昼夜が同じ長さになる日です。春分を境に、本格的な春が訪れます。
昼夜が同じ長さになる日です。春分を境に、本格的な春が訪れます。

2020年の春分は3月20日金曜日となります
4月:清明 せいめい 4月5日頃
 花が咲き、蝶が飛び、鳥がさえずり始めるころです。すべてのものが生き生きとする季節の訪れを表しています。
花が咲き、蝶が飛び、鳥がさえずり始めるころです。すべてのものが生き生きとする季節の訪れを表しています。
2020年の清明は4月4日土曜日となります
4月:穀雨 こくう 4月20日頃
 穀物を潤す春の雨が降る頃です。降雨の終わりには茶摘みや種まきの目安となる八十八夜が訪れます。
穀物を潤す春の雨が降る頃です。降雨の終わりには茶摘みや種まきの目安となる八十八夜が訪れます。

2020年の穀雨は4月19日日曜日となります
5月:立夏 りっか 5月6日頃
 草木がぐんぐん成長し、夏の気配が漂い始めます。子供の成長を祝う端午の節句もこの頃となります。
草木がぐんぐん成長し、夏の気配が漂い始めます。子供の成長を祝う端午の節句もこの頃となります。
2020年の立夏は5月5日火曜日となります
5月:小満 しょうまん 5月21日頃
 日に日に暖かく、いのちが満ちていく頃です。秋にまいた麦に穂がつき、梅の実が膨らみ始めます。
日に日に暖かく、いのちが満ちていく頃です。秋にまいた麦に穂がつき、梅の実が膨らみ始めます。

2020年の小満は5月20日水曜日となります
6月:芒種 ぼうしゅ 6月6日頃
 日差しが十分に暖かくなる頃で、昔から稲や麦など、穂の出る作物の種をまく目安とされています。
日差しが十分に暖かくなる頃で、昔から稲や麦など、穂の出る作物の種をまく目安とされています。
2020年の芒種は6月5日金曜日となります
6月:夏至 げし 6月21日頃
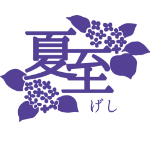 1年でもっとも日が長くなる頃です。夏至以降、日に日に暑くなります。
1年でもっとも日が長くなる頃です。夏至以降、日に日に暑くなります。

2020年の夏至は6月21日日曜日となります
7月:小暑 しょうしょ 7月7日頃
 梅雨があけて本格的な夏を迎える頃です。日差しは強くなり、暑中見舞いを出しはじめる頃です。
梅雨があけて本格的な夏を迎える頃です。日差しは強くなり、暑中見舞いを出しはじめる頃です。
2020年の小暑は7月7日火曜日となります
7月:大暑 たいしょ 7月23日頃
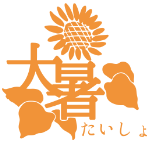 1年でもっとも暑い時期です。花火や風鈴、土用うなぎなどの夏の風物詩が暑さを和らげてくれます。
1年でもっとも暑い時期です。花火や風鈴、土用うなぎなどの夏の風物詩が暑さを和らげてくれます。

2020年の大暑は7月22日木曜日となります
8月:立秋 りっしゅう 8月7日頃
 暑さの中にも、ほんの少し秋の気配が垣間見える頃です。暑中見舞いは立秋の前日までに出します。
暑さの中にも、ほんの少し秋の気配が垣間見える頃です。暑中見舞いは立秋の前日までに出します。
2020年の立秋は8月7日金曜日となります
8月:処暑 しょしょ 8月23日頃
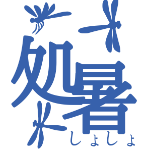 暑さが少しずつ和らぎはじめ、明け方や夕方などに秋の気配を感じます。作物の収穫も間近になります。
暑さが少しずつ和らぎはじめ、明け方や夕方などに秋の気配を感じます。作物の収穫も間近になります。

2020年の処暑は8月23日日曜日となります
9月:白露 はくろ 9月8日頃
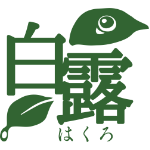 朝夕に大気が冷えて、草木に露がつく頃です。ようやく残暑も終わり、本格的な秋が始まります。
朝夕に大気が冷えて、草木に露がつく頃です。ようやく残暑も終わり、本格的な秋が始まります。
2020年の白露は9月7日月曜日となります
9月:秋分 しゅうぶん 9月23日頃
 秋のお彼岸の中日です。昼と夜の長さが同じになり、秋分以降は夜長になります。
秋のお彼岸の中日です。昼と夜の長さが同じになり、秋分以降は夜長になります。

2020年の秋分は9月22日火曜日となります
10月:寒露 かんろ 10月8日頃
 空気に寒さが混ざりはじめ、草露が冷たく感じられます。空気が澄んで空が高く感じられます。
空気に寒さが混ざりはじめ、草露が冷たく感じられます。空気が澄んで空が高く感じられます。
2020年の寒露は10月8日木曜日となります
10月:霜降 そうこう 10月23日頃
 秋が終わる頃です。朝方や夕方などにはぐっと冷え込むようになり、山では霜が降り始めます。
秋が終わる頃です。朝方や夕方などにはぐっと冷え込むようになり、山では霜が降り始めます。

2020年の霜降は10月23日金曜日となります
11月:立冬 りっとう 11月7日頃
 山里に冬の寒さが忍び寄る頃です。日はいよいよ短くなり、木々は葉を落として寒々と見えます。
山里に冬の寒さが忍び寄る頃です。日はいよいよ短くなり、木々は葉を落として寒々と見えます。


2020年の立冬は11月7日土曜日となります
11月:小雪 しょうせつ 11月22日頃
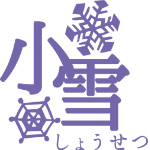 本格的な寒さにはまだ遠いものの、少しずつ肌寒くなり、北国や山の頂に雪が降りはじめます。
本格的な寒さにはまだ遠いものの、少しずつ肌寒くなり、北国や山の頂に雪が降りはじめます。
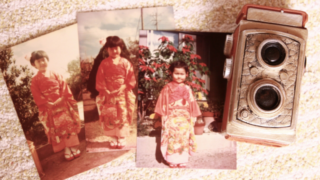
2020年の小雪は11月22日月曜日となります
12月:大雪 たいせつ 12月7日頃
 北風が吹いて寒さが厳しくなりはじめます。山々に降る雪も次第に多くなります。
北風が吹いて寒さが厳しくなりはじめます。山々に降る雪も次第に多くなります。
2020年の大雪は12月7日月曜日となります
12月:冬至 とうじ 12月22日頃
 1年で一番昼が短い日となります。かぼちゃを食べる、柚子湯に入るなどの習慣もあります。
1年で一番昼が短い日となります。かぼちゃを食べる、柚子湯に入るなどの習慣もあります。

2020年の冬至は12月21日月曜日となります
五節句と雑節
旧暦においては、二十四節気・七十二候だけに限らず、季節の節目を意味する五節句と雑節があります。
五節句は当初から邪気を払う時に用いる儀式だったのです。
雑節は農作業の判断材料として、より明確な季節の変化を知るために用いられていたわけです。
現代ではいずれにしても年中行事ということで親しまれています。
五節句
- 人日(じんじつ)の節句は1月7日
- 上巳(じょうし)の節句は3月3日
- 端午(たんご)の節句は5月5日
- 七夕(しちせき)の節句は7月7日
- 長陽(ちょうよう)の節句は9月9日
雑節
- 節分は2020年2月3日月曜日
- 八十八夜は2020年5月1日金曜日
- 入梅は2020年6月10日水曜日
- 半夏生は2020年7月1日水曜日
- 二百十日は2020年8月31日月曜日
- 土用は2020年1月18日土曜日、4月16日木曜日、7月19日日曜日、10月20日火曜日
- 彼岸は2020年9月19日土曜日