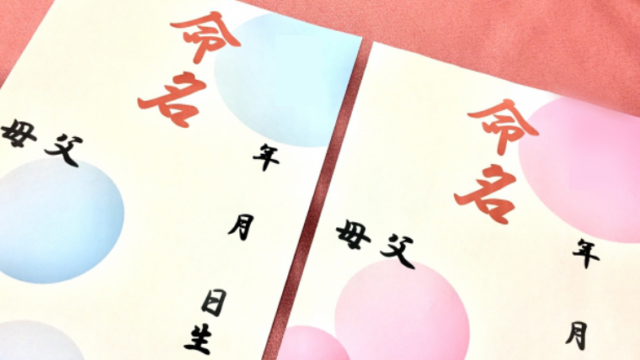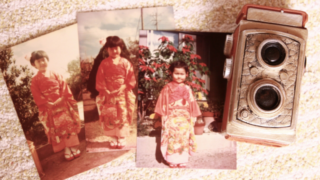12月の師走では一年の終わりの月となり、慌ただしくなります。僧(師)でさえも走り回るので、「師走」と呼ばれるようになったと言われています。
12月の年中行事
12月の年中行事
| 12月7日頃 | 大雪 |
|---|---|
| 12月上旬~下旬 | お歳暮 |
| 12月13日 | 正月事始め |
| 12月15日 | 年賀状受付 |
| 12月中旬~下旬 | 歳の市 |
| 12月22日頃 | 冬至 |
| 12月23日 | 天皇誕生日 |
| 12月25日 | クリスマス |
| 12月28日 | 官庁御用納め |
| 12月31日 | 大晦日 |
師走の正月事始め
12月13日はずっと昔から正月の準備を始める日とされていて、かつては年神様を迎える神棚などのすすを竹竿の先にわらをつけたすす梵天という道具で払う「すす払い」から始めるのがしきたりだったのです。今となっても神社や寺では「すす払い」が行われていますが、一般家庭では12月 13日という日取りに関係なくに、大掃除が行われています。
年末に近づくにつれて、おせちの準備や買い物などで忙しくなることもあって、大掃除は一度にやろうとせず、日頃手がまわらない場所の掃除から徐々に始めましょう。計画を立てる場合には、年末のゴミ収集日も考慮し、無理のないように設定することも大切です。
また、換気扇や窓拭きなどの力仕事は男性にお願いするなど、家族おのおの役割を分担すると、効率よく終えることができるばかりか、家族そろって新年を迎える準備をすることの大切さも感じられるでしょう。

師走のお歳暮
常日頃お世話になっている人や仕事の取引先などに、贈り物と一緒に感謝の気持ちを伝えるお歳暮。12月初旬から20日頃にわたって贈るのが一般的ですけれども、以前は年神様へのお供え物を持って親元などへ出向き、年末のあいさつをしていたこともあって、正月事始めの13日以降に行われていました。



師走の冬至
二十四節気のひとつ。太陽が最も南に位置するため、北半球では一年で一番昼の時間が短くなります。また、冬至を過ぎてしまうと日照時間がだんだん長くなってしまうため、昔は太陽の力が最も弱い陰が極まる日から、再び陽に転じる「一陽来復」と呼ばれ、冬至を境に運気が上昇すると考えられていました。
冬至の健康維持のためにできること
ちょうど寒さが本格的になる時期であることによって、健康維持のための習慣が現在にも伝えられています。 代表的なものがゆず湯になります。本来は「一陽来復」にそなえて体を清めるた めの禊だったのです。ゆずには血行促進や冷え症の緩和、風邪予防などの効果があるとされ、美肌効果も期待できます。また、ゆずの芳香は気持ちをリラックスさせてくれるはずです。
また、冬至にほなんきん(かぼちゃ)、れんこん、にんじんなど、「ん」のつくものを食べると幸運が訪れるといわれています。これは縁起かつぎだけでなく、厳しい冬を乗り切るために必要な栄養を摂るための知恵でもあります。とくにかぼちゃはビタミンAやカロテンが豊富です。保存もきくため、風邪予防に役立つ食材のひとつです。
クリスマス
クリスマスはイエス・キリストの誕生を祝う記念日です。欧米諸国などにおいては、前日のクリスマス・イブに教会でクリスマス礼拝が行われるのです。日本では宗教色は溥く、家族や友人、恋人などと過ごす年に一度の楽しいイベントとして親しまれています。
クリスマスツリーの由来
クリスマスの飾りで街中や家々が彩られますが、その代表であるクリスマスツリーは、古代ゲルマン人が生命力の象徴として常緑樹であるモミの木を飾ったのが始まりと言われています。
サンタクロース
子どもたちが楽しみにしているサンタクロースは、4世紀頃の聖人セントニコラウスが、夜中に貧しい少女たちが住む家の煙突に金貨を投げ入れたのですが、暖炉に下げてあった靴下に入って、少女たちが救われたというような伝説から誕生することになりました。赤い服はキリスト教の司祭服が元になっていますが、国によっては色が異なってきます。
師走の大晦日
毎月最後の日を「晦日」と言っているのですが、12月31日は「大みそか」と呼ぼれ、一年を締めくくるためのたくさんのしきたりがあるのです。
年越しそば
大みそかに縁起をかついでそばを食べる風習というのは江戸時代から始まりました。細く長いそばに、健康長寿や家運長命というような願いが込められているというわけです。食べる時間は地方によってまちまちで、大みそかのタ食や日付が変わる深夜に食べることもあります。
除夜の鐘
深夜0時近くから、いろんな地域の寺院で鐘をつき始めます。鐘を仏教で人間が持つ煩悩の数といわれる108回つくことで煩悩が追い払われると言われています。107回までを年内に、最後の1 回を新しい年につきます。
「除夜」というのは眠らない夜という意味で、これまでに大みそかの晩に神社にこもり夜を明かすという「年籠(としごもり)」という習わしから、大みそかを「除夜(じょや)」と呼ぶようになったのです。