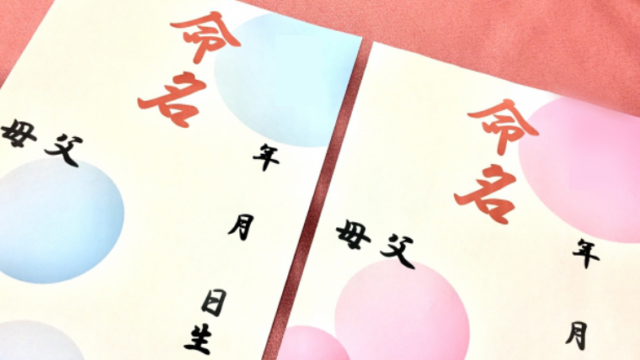赤ちゃんが生まれて100日頃に行う行事が「お食い初め(おくいぞめ)」または「百日祝い」と言われるものです。
お食い初めとはなんだろう?何のためにおこなうのだろう?何をすればいいの?と思うパパママもいると思います。
健やかに成長してほしい赤ちゃんのお祝いなら、是非とも祝っておきたいと思うパパママ。
どうやって祝えばよいのか、さっぱり分からないというご両親に今回は記事を書きたいと思います。
お食い初めの意味は?
お食い初めはいつ?
お食い初めとは?
「お食い初め」とは、わが子が一 生食べ物に困らないようにという願いを込めて行う儀式だとされます。
近いうちに離乳食にチャレンジする生後100日めに行われるものであり、両親、祖父母が揃って祝い膳を囲みます。
正確に言えば母方の実家から漆器膳を贈り、一番長寿の人が「養い親」ということで赤ちやんを膝に抱いて食べさせるまねを行ないます。
近年では、お食い初めセットが販売されているなど、レンタルも見受けられます。そして、離乳食のおかゆを用意するなど略式に行うことも多くなっている様子です。
お食い初めの意味
お食い初めの儀式の意味はなんなのでしょうか?
ここでは、赤ちゃんの100日目のお祝いのお食い初めの意味についてご紹介しましょう。
お食い初めのとは、我が子が「一生食べることに困らないように」と願って行われる儀式です。
この「お食い初め」という呼び名は地方によって呼び方が変わることがあります。
「百日祝い(ももかいわい)」、「箸始め」、「箸揃え」、「歯固め」、「真魚はじめ(まなはじめ)」などと呼ばれます。
いずれの儀式も生後100日目頃に行われるのが一般的ではありますが、地域によっては110日目であったり120日目になることもあります。
あくまでもおおよその目安として捉え、家族の都合なども相談して、赤ちゃんの成長をみんなで祝える日取りにするのが良いでしょう。
お食い初めの所作というもの地域それぞれによって様々なので、いつ行うのかや準備するもの、鯛あるいは歯固め石などの献立メニューや調理法など、儀式のやり方・マナーなど悩まれる事も多いようです。
ここではあくまでも、一般的な事例としてご紹介するので、住んでいる地域の習わしと合わせて行うように判断基準としてみることをおすすめします。
地域によって「お食い初め」の呼び名が違う
- 百日祝い(ももかいわい)
- 箸始め
- 箸揃え
- 歯固め
- 真魚はじめ(まなはじめ)
お食い初めはいつ?誰を招いておこなえばいいの?
お食い初めの時期については、前述したとおり、赤ちゃんの100日目に祝うというのが一般的で、地域により110日目であったり120日目であったりします。
ただ、あまり100日目にこだわることなく、家族で相談して、100日付近で祝える日にお食い初めの儀式をするといいということです。
では、誰とお食い初めをしてらいいのか?
儀式でいえば母方の実家から漆器膳を贈り、一番長寿の人が「養い親」ということで赤ちやんを膝に抱いて食べさせるまねを行ないます。
昔は親戚や知人を招いて盛大に行うこともありましたが、近年では赤ちゃんと両親や祖父母だけの家族で行うことが多くなっています。
また、自宅で行うのではなく、レストランやホテル、座敷などでおこなう方も増えています。
ただ、外食となると赤ちゃんの健康状態やお世話できる設備や場の雰囲気などが気になるところですよね。
まとめ
赤ちゃんがいよいよ離乳食を始める大事な節目の行事となる「お食い初め」。
子どもが一生食べることに困らないようにと願うのはみんなの願いです。
祖父母も可愛い赤ちゃんに会えるまたとない機会ですから、みんなで祝うと笑顔が溢れますよ。
準備には何が必要なのか気になる方は下記の記事もあわせて読んでみてください。