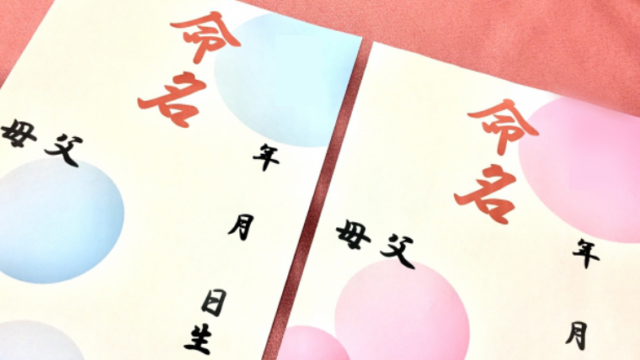赤ちゃんが生まれて100日頃に行う行事が「お食い初め(おくいぞめ)」または「百日祝い」と言われるものです。
もともとは貴族階級がとりおこなう行事であったと言われ、お食い初めにはどんなお膳をあつらえるのがいいのか?器には何を使うのがいいのか?といった細かな決まり事があるわけですが、ここでは、そんなお食い初めにぴったりな食器はどんなものがいいのかをご紹介しましょう。
また、お食い初めに並ぶ鯛や煮物、歯固め石の準備をどのようにすればいいのかなどまとめてみました。
・お食い初めの献立は?
・歯固め石の準備はどこで?
お食い初めの「祝い膳」とは?
お食い初めで赤ちゃんに食べさせる料理のことを「祝い膳」と呼びます。
一汁三菜の献立で整えるのが一般的で、祝い膳には、脚付きの塗りお膳を使うのが正式です。
お膳 脚付きの漆塗りのお膳
食器 食い始め椀(赤飯を入れます)
汁椀 ハマグリ潮汁
平皿 尾頭付きの鯛
小鉢 煮物など
高坏 香の物など
白木の箸、鶴や松なそおめでたい蒔絵び漆器椀、紋付の漆器の膳で脚が付いたものが正式となります。
食器の色は男の子と女の子で違う?
「祝い膳」として使う漆器というのは、赤ちゃん1人1人に新品をあつらえます。どうしてかというと、お膳を使って食事を摂っていた時代、「お食い初め」の時に作ったお膳を子ども用の食器としてある程度の年齢になるまで愛用していたからというもの。
その日使うだけのものというのではなく実用品となっていました。
現在でもお箸や茶碗を見ると男女で色や柄が違うように、日本では使う人に合わせて食器を変える習慣があるというわけです。
これによって「祝い膳」の漆器も男の子は外内側ともに朱色、女の子は外側が黒、内側が朱の色の塗り物を使います。絵付けや蒔絵の柄も、赤ちゃんが男か女かで選ぶ文様が違います。
男の子の食器によく使われる文様は日輪や菖蒲などは運気や元気さを表現する文様
女の子の食器によく使われる文様は優雅なものが多く、花文様や束ね熨斗の文様
100円均一などでも代用できそうな食器は販売しています。
赤ちゃんの初めての食器としてしっかりとしたものを選ぶのであれば、ネットでも一式を簡単に揃えることができます。
祝い膳にはミッキーマウスなどのキャラクターのものもあります。
もちろん男の子用と女の子用があります。
お食い初めの献立
赤飯、尾頭つきの焼き魚、すまし汁、煮物、ナマス(または香の物)をそろえて一汁三菜の5品にするのが基本的です。
二の膳として紅白餅を用意することもあります。
地域によっては石を噛めるほどに丈夫な歯になるようにと願いを込めて「歯固めの石」(神社の境内からいただいて洗って添える)や長寿を表すシワシワになるまで長生きするようにと「梅干し」を添えたり、喜ぶことから「昆布」を添えることもあります。
通販も検討のに入れてもいいかもしれません。
一生に一度のお食い初めの儀式に高級料亭のお食い初めセットを注文すると、お食い初めに必要なものすべてと儀式解説書などが付属しているので安心です。
また、子育てで忙しいパパママがお食い初めの食材を料理するのは一苦労です。
そんな時は通販で美味しい「お食い初め膳」を頼むのも一つの手です。
尾頭付きの鯛
おめでたい席のお魚と言えばなんといっても「鯛」だと言えます。
なぜ鯛が選ばれるかと言われると、表面が赤色で身は白と、縁起のいい紅白の色だということと、めで「たい」という語呂も良いこともあって、縁起物の魚として定着していると考えられます。それから、魚の中では寿命が長いことでも知られています。
自宅でお食い初めをする時には、スーパーや魚屋さんで鯛を買うこともできますが、尾頭付きの鯛というのは、毎日売っているわけではないのです。
事前に魚屋さんに「お食い初め用に」と予約を入れておくと良いでしょう。また、ネット販売でも尾頭付きの鯛を購入することができます。自宅のグリルで焼くことになると失敗したり、尾っぽが上を向かなかったりといろいろと大変です。
ここは失敗しなことを考えると、ネット販売の鯛を購入するのが個人的には近道と感じます。
はまぐりのお吸い物
一汁三菜の「一汁」ということで、はまぐりのお吸い物(椀もの)が供される場合が多いです。
お吸い物は「吸う」力が強くなるという意味があるとは別に、はまぐりは、もともとの2枚の貝殻じゃないとうまく重なり合わないという性質があることから、生涯の伴侶を意味しており、「良縁に恵まれますように」という意味が秘められているというわけです。
煮物
煮物は特に決まりというものはなく、旬の食材を使用するのが一般的です。
縁起の良い食材からすれば、人参と大根で紅白を表現したり、タネイモに小芋がたくさん付くことから「子宝に恵まれますように」という願いを含ませて里芋を添える場合もあります。
この他には、すくすくと育つようにという願いからタケノコ、見通しの良い人生をという願いでレンコンなどを入れたりしていきます。地域や家庭の風習によってなにやかやと違うので調べてみると安心できると思います。
香の物(こうのもの)
香の物としては、「梅干し」を添えます。
梅干しは「梅干しのように、しわができるまで長寿に生きられますように」というような願いからだといえます。
きゅうりなどの酢の物でもかまいません。
地域によってはタコや栗を出すところもあるのです。
これ以外には、香の物(こうのもの)とは、いわゆるお漬物のことですが、こちらも縁起をかついで「幸(こう)」とかけて、わざわざ香の物と言っているのです。
基本的にはその土地の名産や旬の野菜を漬けたものが供されますが、にんじんと大根をせん切りにしてお酢で和える「紅白なます」を添える家庭も多いとのことです。
赤飯
おめでたい日に供されることの多い赤飯。
赤色の小豆と白色の白米を使って「紅白」を表していることは、ご存知のことかと思います。
赤飯には、魔除けや厄払いの意味合いがあり、紅白の紅の色は邪気を追い払うと言われ縁起が良いという説もあります。
お食い初めでは赤飯以外にも、白いご飯やお粥、栗ご飯を用意するところもあるようです。ご飯の代わりにお餅を用意しても構いません。
歯固めの石
お食い初めでは、「赤ちゃんの歯が石のように丈夫に育ちますように」との願いを込めておこなわれる「歯固め」というような儀式があるのです。
この歯固めという儀式とは「歯固め石」と呼ばれる石を用意し、お箸で歯固め石に触れてから、そのお箸で赤ちゃんの口にチョンチョンとあてます。
赤ちゃんの歯ぐきに歯固め石をあてる地域もあるのです。
「歯固め石」は、氏神様である神社に出向き、そこにある石を借りてくるのが慣例となっているのです。
お宮参りのご祈祷の際に、祝い箸と歯固め石をいただける神社もあるようです。氏神様の神社から石を持ち帰るのがはばかれるといった場合では、歯固め石が販売されているところもあるので、購入してもいいでしょう。
持ち帰った歯固め石は、お食い初めが終わったらきれいに洗って、感謝の気持ちを込めて神社に返すと良いでしょう。
歯固め石は1~2個あれば問題なしです。
今では歯固めの石も販売されていますから、簡単に準備ができます。