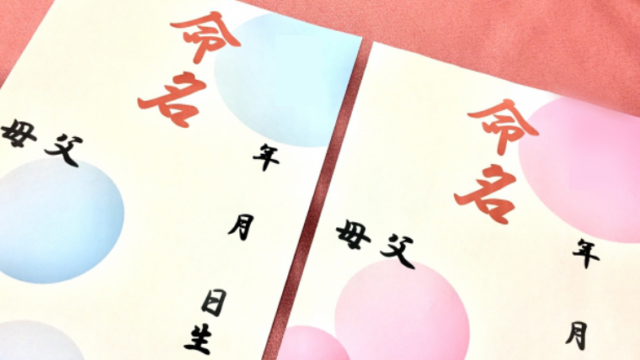11月になると本格的に霜が降り、寒さが厳しくなる時期なので、「霜月」あるいは「霜降月」と呼ばれています。
11月の年中行事
| 11月3日 | 文化の日 |
|---|---|
| 11月7日 | 立冬 |
| 酉の日 | 酉の市 |
| 11月15日 | 七五三 |
| 11月22日頃 | 小雪 |
| 11月23日 | 勤労感謝の日 |
霜月の酉の市
江戸時代から続く年中行事,毎年11月の酉の日に、開運や商売繁盛の神とされる鷲明神を祀る各地の鷲(大鳥)神社で行なわれます。酉の日というのは午によって2~3回ありますので、最初の酉の日を「一の酉」、次を「二の酉」、3回目を「三の酉」と言っています。三の酉まである年は人事や災いが多いという故事も残されています。
酉の市を代表する縁起物は、熊手です。熊手には、「運をかき集める」という意味があり、七福神や宝船・鶴亀、大判小判など、縁起のよい飾りが施された、豪華な熊手が露店で売られています。いっそう招福を願い、毎年少しずつ大きいものに買い替えていくのがよいとされています。店主と客が露店の店先で値切りをして、折り合いがつくと威勢のよい手締めが行われるのも、酉の市ならではの光景だと言えるでしょう。
熊手の飾り方
熊手というのは、神棚の上などの高い場所に飾り、手を南か東に向けます。神棚がない場合は玄関に飾りましょう。その場合は、外から福をかき込むよう、手をドアに向けますが、北向きは避けましょう。
霜月の文化の日
元々は明治天皇の誕生日で、明治天皇が亡くなってというもの「明治節」ということで、明治天皇の偉業をたたえる祝日になったのです。それから後に、1946 年11月3日に日本国憲法が公布が行われ、平和と文化を重んじた憲法を記念して、 1948年に「文化の日」として制定されました。
毎年この日には、皇居で科学技術や芸術などの文化の発展に貢献した人々へ文化勲章や各褒章を授与する、親授式が催されます。
霜月の七五三
男女ともに3歳になると髪を伸ばし始める「髪置き」の儀式であったり、武家や宮中の儀式が江戸時代に広く一般に広まり、子どもの健やかな成長に感謝して、氏神様をお参りする風習となったのです。以前は数え年で祝っていたのですが、現在では満年齢を迎える年に行われるのが一般的です。男の子は3歳と5 歳、女の子は3歳と7歳に祝います。


霜月の勤労感謝の日
「勤労を尊び、生産を祝い、国民がお互いに感謝し合う」ことを目的として、 1948年に制定された国民の祝日だということです。それまでは「新嘗祭」と言われていて、その年の収穫に感謝する行事がおこなわれていました。
「新嘗祭」の歴史は飛鳥時代から始まったといわれ、天皇がその年に収穫した五穀を供え、それを食する宮中行事が行われてきました。その宮中行事は現在でも続けられ、全国の神社でも同様の行事が行われています。