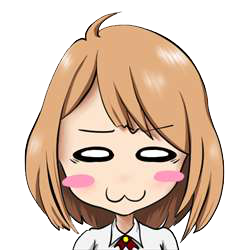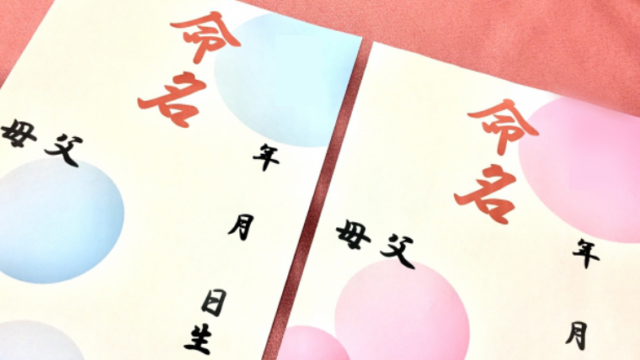如月の由来には諸説あり、寒さが厳しくなる時期なので、これまで以上に衣を重ねて着る「衣更着(きさらぎ)」となったとも言われています。
みほし
2月はバレンタインデーがありますね。れんさん!チョコお待ちしています♪
れん
僕が美星さんにあげるんですか!?逆じゃない?まぁ・・海外では男女問わず贈り合いますしね・・
2月の年中行事
| 2月1日 | 旧正月 |
|---|---|
| 2月3日頃 | 節分、豆まき |
| 2月4日頃 | 立春 |
| 2月6日頃 | 初午 |
| 2月8日 | 針供養(事はじめ) |
| 2月11日 | 建国記念日 |
| 2月14日 | バレンタインデー |
| 2月19日頃 | 雨水 |
節分
立春の前の日を節分と言っているのですが、かつては立春、立夏、立秋、立冬の前日を節分と表現していました。
節分には、季節の変わりめに起こりやすい病気や災害を追い払い、福を呼び込む「豆まき」をおこないます。家中の窓や戸口を開け放ち、「鬼は外」と言いながら外に向けて2回、「福は内」と言いながら家の中に向かって2 回豆を投げるのです。まき終わったら、自分の年の数だけ豆を食べて、一年間の健康を願います。ヒイラギの枝にいわしの頭を刺したものを軒先につるし、魔除けにする場合もあります。
針供養
折れ曲がったりして使いものにならない針を仏前に供え、仕事道具の針に感謝し、裁縫の上達を祈る行事12月8日(事納め)にもおこなわれるケースがあります。
バレンタインデー
3世紀のローマ時代、恋愛を禁止されていた兵士たちは、バレンチヌス司教の元で密かに結婚式を挙げていました。ところが、皇帝の怒りを買った司教は2月14日に処刑されてしまいます。のちに司教の命日は「愛の日」とされ、司教へ感謝を捧げるようになったのが、バレンタインデーの始まりだといわれています。
女性から男性にチョコレートを贈るのは、日本独自の習慣。海外では、男女問わずプレゼントを贈り合います。

弥生の3月はひなまつりやお彼岸やホワイトデーなどの年中行事弥生(やよい)には、草木がより一層生い茂るといった意味があります。夢見月(ゆめみづき)というような別名で呼ばれることもあります。...
ABOUT ME