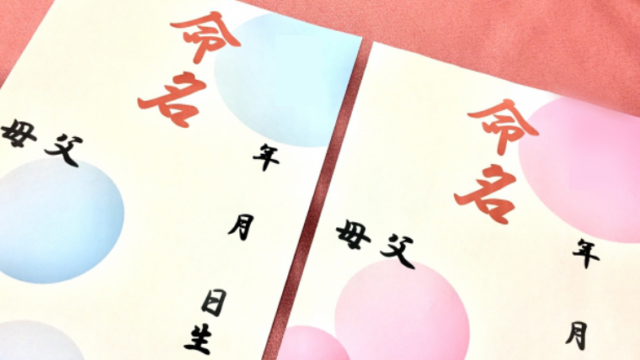日を追うごとに夜が長くなる時期となるため、「夜長月」が語源となり、菊が美しい季節ということもあり、菊咲月(きくさづき)という異名もあります。
9月の年中行事
9月の年中行事
| 9月1日 | 防災の日 |
|---|---|
| 9月1日頃 | 二百十日 |
| 9月8日頃 | 白露 |
| 9月9日 | 重陽の節句 |
| 9月中旬~下旬 | お月見(十五夜) |
| 9月第3月曜日 | 敬老の日 |
| 9月20日頃 | 彼岸入り |
| 9月23日頃 | 秋分の日 |
長月の防災の日
1923年(大正12年)9月1日に関東大震災が起こりました。死者・行方不明者が14方人を越えるほどの甚大な被害がもたらされ、そのほとんどは地震後の火災による被害だったと言われています。さらに、 9月1日頃は、立春から数えて210 日めにあたる「二百十日」とされていて、台風が来襲する厄日でもあることもあって、国民の防災に対する意識を喚起することもあって、1960年に「防災の日」として制定されました。防災の日を含む1 週間を「防災週間」として、各地で防災知識普及をめざしたイベントなどが実施されてます。
長月の重陽の節句
重陽の節句は古代中国から伝えられた五節句のひとつとして、別の呼び名で「菊の節句」ともいわれます。中国では奇数を縁起のよい陽の数字と考えられ、とくに最高の場数である9が重なる9月9日はとてもおめでたい日ということで、不老長寿の薬として珍重されていた菊の香を移した菊酒を飲むなどすることで、厄を祓い長寿を願う風習がありました。 この風習が日本に伝わったのは平安時代にさかのぼり、宮中では詩を詠んだり菊酒を飲んだりする「菊花宴」が行われるようになりました。庶民の間では栗ご飯を炊いて無病息災を祝ったことから「栗節句」という異名もあります。
重陽の節句は、以前は「お九日(おくんち)」として広く親しまれていました。「長崎くんち」など、九州の有名な秋祭りはその名残と言われています。
長月の敬老の日
1966年に国民の祝日ということで制定された「敬老の日」というのは、社会のために貢献してきた高齢者への感謝を込めて、長寿をお祝いする日になります。 2002年までは9月15日だったんですが、ハッピーマンデー制度の実施それによって、 2O03牛から第3月曜日になったというわけです。また、9月15日から1週間は「老人週間」とされています。
長月のお月見(十五夜)
旧暦の8月15日である9月中旬から下旬というのは、一年で最も美しい月が出現する時期ということもあって、日本では古くから満月を愛でる行事がなされててきました。
お月見の起源というのは、家族が集まって月餅を食べて、満月を祝うというような中国の「中秋節」といわれています。平安時代には、貴族の間で「観月の宴」がおこなわれるようになりました。
この他には、日本独自の風習として、旧暦の9月13日にあたる10月中旬~下旬にもお月見(十三夜)を行ないます。
お月見(十五夜)のお供え物
ちょうど秋の収穫期にあたることにより、農作物や月見だんごを供えて、豊作を祈願するものです。地域によってお供えものは異なってきますが、月見だんごやおはぎ、秋の七草(はぎ・すすき・くず・なでしこ・おみなえし・ふじばかま・ききょう)だけに限らず、その時期に採れた作物を供えることだってあります。
長月の秋のお彼岸
星夜の長さが同じになる秋分の日 (9月23日頃)を中日には、前後3日間ずつの1週間が秋のお彼岸となります。春のお彼岸と同様に、お墓参りをして先祖の霊を供養するわけです。お墓や仏壇には、花やおはぎ、彼岸だんごなどを供えます。お墓参りにおいては、なるべく家族そろって出かけ、墓前で手を合わせて、近況報告や見守ってくれていることへの感謝を、心を込めて伝えたいものです。
お寺では読経や法話などを行う「彼岸会」といった法要が営まれています。できるのだと彼岸会にも参加し、先祖の霊の供養をお願いしましょう。参加できなくても、ご本尊様にお参りをし、お寺の住職にあいさつをするのを忘れないようにしましょう。