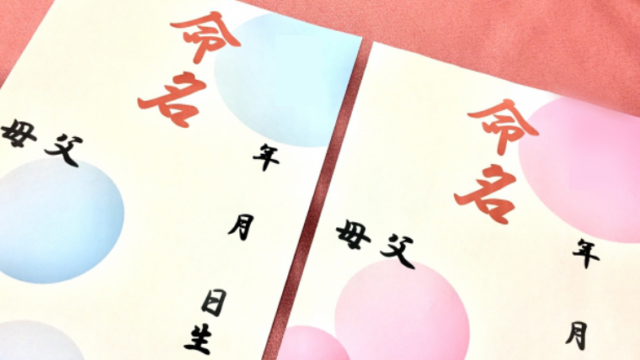木々の葉が舞い落ちる「葉落月」が略されて「葉月」になったという説が有力です。異名は旧暦ということなので、秋に由来しています。
8月の年中行事
8月の年中行事
| 8月2日~7日 | 青森ねぶた祭 |
|---|---|
| 8月6日 | 広島原爆の日 |
| 8月6日~8日 | 仙台七夕まつり |
| 8月8日頃 | 立秋 |
| 8月9日 | 長崎原爆の日 |
| 8月15日 | お盆 |
| 8月15日 | 終戦記念日 |
| 8月16日 | 送り火 |
| 8月16日 | 精霊流し |
| 8月23日 | 処暑 |
お盆
お盆には先祖や亡くなった人たちの霊を供養するための・日本を代表する風習とされるものです。期間は地域それぞれによって異なってきますが、8月13日~16日が一般的です。13 日は祖先の霊を迎える「迎え盆」、16 日は祖先の霊を送り出す「送り盆」と言われています。
お盆の由来
お盆は仏教語の「孟蘭盆会(うらぼんえ)」の略語です。孟蘭盆会はサンスクリット語の「ウランバナ」の音訳で、ウランバナには「逆さまにつるされた苦しみ」という意味があり、孟蘭盆会では先祖の霊をその苦しみから救うために供養を行ないます。 これは、お釈迦様の弟子である目連が、餓鬼道に落ちて苦しむ亡くなった母親を救うために、お釈迦様の教えにしたがって供養したところ、母親の霊を救うことができた、という仏教の故事に由来しています。
お盆の盆棚(精霊棚)
13日の朝に、祖先の霊を迎える準備をします。仏壇がある場合は掃除をし、盆棚(精霊棚)をととのえます。 正式には四隅に青竹を立て、ほおずきを吊るした棚を作りますが、仏壇の前に小さな机を置いて作る略式の方法が一般的です。
お盆の迎え火
8月13日のタ方ともなると、庭先や玄関先で迎え火を焚き、祖先の霊を迎えるのです。迎え火は、焙烙(素焼きの皿)の上に麻幹(おがら)を折って「井」の形に組んで火をつけます。マンションなどで火を焚くのが困難な場合は、玄関灯をともすだけでも構いません。
お盆の送り火
16日の「送り盆」であれば、迎え火と同じように火を焚き、先祖の霊を送りだします。送り火の風習は地域によって特色があって、京都の東山如意ケ嶽等に点火される「五山送り火」、供物を乗せた盆舟に灯をともして海に流す長崎の「精霊流し」などが有名です。
お盆の盆踊り
戻ってきた先祖の霊を供養するべく行われる仏教行事となります。念仏踊りと孟蘭盆会が結びついたと言われています。
終戦記念日
1945年8月15日、日本の敗戦を伝える昭和天皇の終戦詔書がNHKラジオで流され、太平洋戦争(第二次世界大戦)が終結しました。終戦記念日には日本武道館で全回戦没者追悼式が行われています。