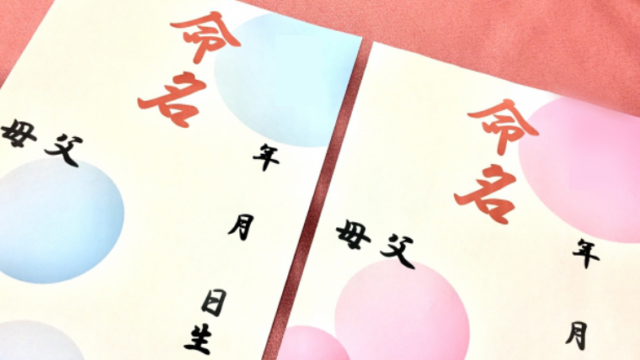水無月は月でいうと6月です。農作業をすべて終えた月を意味して「みなしつく月」が略されて「みなづき」となったという説があったり、暑さで水が無いといういいつたえから水無月となったといういわれもあります。
6月の年中行事
6月の年中行事
| 6月1日 | 衣替え |
|---|---|
| 6月6日頃 | 芒種 |
| 6月10日 | 時の記念日 |
| 6月11日 | 入梅 |
| 6月第3日曜日 | 父の日 |
| 6月21日頃 | 夏至 |
| 6月30日 | 夏越しの大祓 |
衣替え
学校や会社の制服については、6月1日に夏服に切り替わり、10月1日に冬服に切り替わりいます。衣替えの始まりは平安時代までさかのぼり、中国の風習に関連して、宮中では旧暦の4月1日に綿入りの着物から綿を抜く「綿貫」をします。10月1日に再び綿を入れる「更衣」を行うようになりました。衣替えの風習が庶民に広まったのは江戸時代になってからになります。
近頃は冷房にかかる電気を節約するため、軽装で出社するクールビズが普通での官公庁や企業で導入されているというわけです。クールビズは5月1日から行われることもあります。
入梅
立春から135日めである6月11 日頃を入梅といい、入梅から30日間が梅雨の時期になってくるのです。しかしながら、実際の梅雨入りや梅雨明けの時期とは異なるのです。
一説では、ちょうど梅の実が熟す季節に雨が降ることもあって「梅雨」と言われるようになったといわれています。また、湿気が高くカビが生えやすい時期であることから「微雨」と書くこともあります。
父の日
20世紀初頭、アメリカ・ワシントン州に住む女性が、母の日と同様に父親においても感謝する日を作るということを提唱したということが、父の日の始まりです。日本国内には1950年頃に広がっていきました。 アメリカでは父の日にバラを贈るのが慣例ではありますが、日本ではネクタイや小物などといった実用品を贈ることのほうが一般的と言えます。
夏至
二十四節気のひとつである夏至(げし)。太陽がいちばん北にくるため、北半球では一年の中で最も昼が長くなりるのです。夏至を越えてしまうと本格的な夏が始まるとされています。
一年の中で最も昼が短くなる冬至だとかぽちゃを食べたり、ゆず湯に入るというような慣習がありますけど、夏至の場合は地方によって異なります。関西地方だったら、八本足のタコさながら稲が深く根を張ることを祈願して、タコを食べる慣習があるのです。
夏越しの大祓
大祓とは、気づかないうちに犯してしまう罪やけがれを取り除くことを願った、6 月と12月の末日に各地の神社でおこなわれる、奈良時代から始められた厄除けということなのです。
6月の祓では、鋭利な葉を持つ茅(ちがや)で作った輪をくぐり、心身の概れを落とす「茅の輪くぐり」という神事がおこなわれます。また、紙を人の形に切り抜いた「人形」に名前と年齢を書き、その人形で体をなでてから息を吹きかけ、海や川などに流すことで、身を清めるわけです。