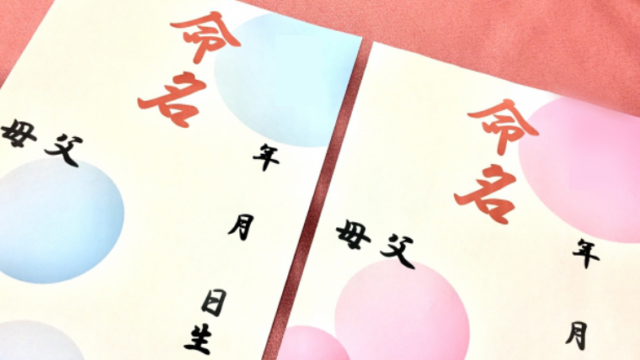弥生(やよい)には、草木がより一層生い茂るといった意味があります。夢見月(ゆめみづき)というような別名で呼ばれることもあります。
関東びなの並びになったのは、大正天皇が即位されたときに、西洋式に左に立たれたことがきっかけと言われています。
3月の年中行事
3月の年中行事
| 3月3日 | ひなまつり |
|---|---|
| 3月5日 | 啓蟄(けいちつ) |
| 3月13日 | お水とり |
| 3月14日 | ホワイトデー |
| 3月18日 | お彼岸入り |
| 3月21日 | 彼岸の中日 |
| 3月21日 | 春分の日 |
| 3月24日 | お彼岸入り |
ひなまつり
女の子の健やかな成長と幸せを願う桃の節句。ひな人形を飾り付け、ちらし寿司やはまぐりのお吸い物等々、ひなまつりにちなんだ料理で祝うものです。祖父母、親類、友人を招待する場合もあります。
ひな人形
ひな人形には、桃の花、白酒・ひなあられなどを供えるのです。七段飾りが通例ですけれど、親王飾りのみのコンパクトなひな人形を飾ることだってあります。
飾る時期は、3月3日の1週間から 2週間前の吉日だとされています。ひなまつりの前の日に飾るのは「一夜飾り」と呼ばれていて、縁起が良くないのでやめた方が良いでしょう。片づけはひなまつりの翌日にしていきます。はたきなどで軽くほこりを払い、人形と小物類を分けて、やわらかい紙に包んでしまいた方がいいでしょう。
ひな人形の飾り方(七段飾り)
| 最上段:親王びな | 向かって左に男びな、右に女びなを置きます。奥に屏風を広げ、ぼんぼりは両脇、お神酒は中央に置きます。 |
|---|---|
| 二段目:三人官女 | 向かって左に銚子持ち、三方持ち、長柄の銚子持ちの順に置きます。高坏は官女の間に置きましょう。 |
| 三段目:五人囃子 | 向かって左から、太鼓、大鼓、小鼓、笛、謡の順に置きます。 |
| 四段目:随身(護衛役) | 向かって左から、右大臣、右に左大臣を置きます。菱台は中央に置きます。 |
| 五段目:仕丁(雑用係) | 向かって左から、台笠持ち、沓第持ち、立傘持ちの順に置きます。膳は仕丁の間に。 |
| 六段目:嫁入り道具 | 向かって左から、箪笥、鋏箱、長持、鏡台、針箱、火鉢、茶道具の順に置きます。 |
| 七段目:嫁入り道具 | 向かって左から、御駕籠、重箱、御所車を置きます。右近の橘を左端、左近の桜を右端に置きます。 |
春のお彼岸
昼夜の長さが同様になるので、極楽浄土の方角である真西に太陽が沈む春分の日というものは、仏の住む世界と現世が交流が可能になる日とされていて、春分の日の前後3日間をお彼岸と呼び、祖先の霊を供養することになります。彼岸入りの前日に仏壇を掃険して、お彼岸の期間中にはお墓参りに足を運びましょう。お墓を掃除し、故人の好物やぼた餅を供えるのです。
春のお彼岸にお供えするもの
お彼岸のお供え物は、春のお彼岸には「ぼたもち」を供えるというのが通例です。ぼたもちとおはぎは一緒の事ですけれど、時期により呼び名が変わっていきます。ぼたもちとされているところは、春になると咲く牡丹の花に関連してぼたもちと呼びます。 日本においては、小豆の赤い色はめでたい色とされていたわけです。
ホワイトデー
日本独自のイベントとして、バレンタインデーに女性からプレゼントをもらった男性が、女性にお返しをする日。お返しの品は、キヤンディやクッキー、マシュマロというようなお菓子、アクセサリーといったものが一般的です。
ホワイトデーと名前を付けられたわけ
ホワイトデーの始まりを考えるうえで欠かすことができないのがホワイトデーの呼び方の始まりです。始めのうちは海外の慣習にならい「フラワーデー」であったり「クッキーデー」に決めるということも検討されていたようです。しかしながら、「純潔」や「純粋な愛のシンボル」ともイメージできる白が想いをお返しする日にはしっくりくるとして「ホワイトデー」に決定されました。