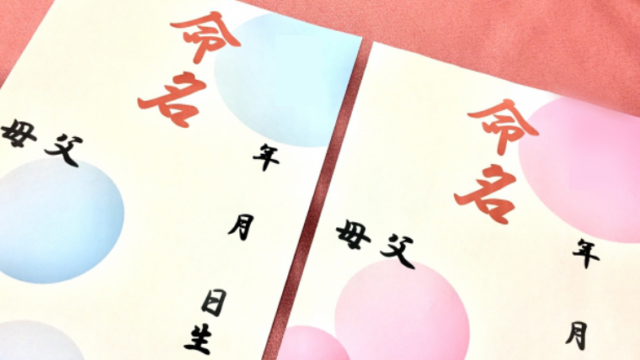お正月になると玄関にしめ飾りを飾るのに買ってきたのはいいけれど、しめ飾りはいつから飾ればいいのか?また、神棚なんて我が家にはないけど、しめ飾りを飾ってもいいのか?飾るためにはどのような準備が必要なのか?あれこれ考えてしまいますよね。
そのような疑問について今回は解決して、新たに迎える新年の準備をして、年神様を我が家へお迎えして素晴らしい一年を願いましょう。
しめ縄としめ飾りの違いはなに?
「しめ縄」と「しめ飾り」の違いはなんでしょうか?
しめ縄の起源は、天照大神が天岩戸から出た際に、二度と天岩戸に入ることができないように、太玉命が注連縄(「尻久米縄」)で扉を塞いだのが起源だとされています。
このようなことから「しめ縄」というのは神様が宿る場所、つまり家庭では神棚に飾っているのです。
そして「しめ飾り」に関しては、しめ縄に願いを込めて縁起物の飾りをつけたのが始まりとされていて、大抵は玄関に飾りつけます。
それには、ここの家は神様を迎えるのにふさわしい場所ですよと伝える意味や、一度家の中に入った神様が出て行かないという理由など諸説あるということです。
すなわち、 神様が宿る場所に飾るというのが「しめ縄」で、迎え入れる場所に飾るのが「しめ飾り」こういうことということですね。
しめ飾りはいつ飾るのがベストタイミングなのか?
仏滅や六曜などに極端にこだわる必要はないですが、できることなら日取りの良い日に飾ることをおススメします。
一般的には12月13日~12月28日までに飾ると良いです。
12月13日は正月事始めといって正月の準備を始める日とされていて、すす払いや一年のホコリを掃除したり、窓を綺麗にしたりします。また、松迎といって門松用の松を切り出しに行く日でもあります。
ほんの少し意識するなら29日は二重苦に通じることから避けて、31日は一夜飾りといって年神様をお迎えするにはあまりにも時間がなく、準備不足で失礼にあたると言われています。
できることなら28日までに年神様を迎え入れる準備をしたいですね。
ちなみにしめ飾りを仕舞うのはいつ頃?
しめ縄やしめ飾りは、松の内が終わる頃に外すのがよいとされます。
松の内というのは、門松を飾っている期間のことで、元々は1月15日までを指していたのです。しかし、1月11日の鏡開きの時にもまだ門松を飾っているのはおかしいと、関東地方では1月7日に松の内を早々に行い、それに合わせてしめ縄などの正月飾りも外すようになったとされています。
一方、関西地方では昔のまま1月15日にしめ縄やしめ飾りを外す地域も少なくありません。 そして、外したしめ縄やしめ飾りは、1月15日に神社で行われる〝どんど焼き〟に出して処分するのが通例です。
神棚がないけどしめ飾りを飾ってもいい?
結論から言って、神棚がなくてもしめ飾りを飾っても構いません。
神棚は通常「三柱の神様」をお祀りする場合が多いです。
ここでいう三柱の柱(はしら)は神様を数える単位を表しています。
三柱の神様とは天照大御神(伊勢神宮)、地元の神様(氏神神社)、好きな神様(崇敬神社)などです。
そして、お正月に迎える神様は年神様です。
年神様とは元旦になると高い山から下りてきて、各家々に新年の幸せをもたらすためにやってくる神様のことです。
しめ飾り同様に鏡餅も年神様をお迎えするためにお供えをします。
しめ飾りを玄関に飾るのは、年神様を迎えるためなので、神棚がなくても問題ありません。
ぜひとも、正月のは年神様を我が家へお迎えしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。しめ飾りについてまとめをしておきます。
神様が宿る場所に飾るというのが「しめ縄」で、神様を迎え入れる場所に飾るのが「しめ飾り」。
しめ飾りを飾るのは12月13日~12月28日までに飾ると良い。
しめ飾りを玄関に飾るのは、年神様を迎えるためなので、神棚がなくても問題なし。
では、よい新年をお迎えください。