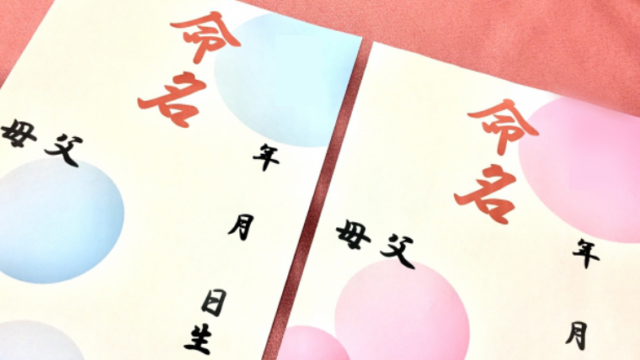田植えで大忙しとなる時期で、早苗を植えることもあって「早苗月(さなえづき)」などとよばれることもありますが、「さつき」と略されてよばれるように変わってきました。
5月の年中行事
5月の年中行事
| 5月1日 | メーデー |
|---|---|
| 5月2日頃 | 八十八夜 |
| 5月3日 | 憲法記念日 |
| 5月4日 | みどりの日 |
| 5月5日 | こどもの日 |
| 5月5日 | 端午の節句 |
| 5月6日 | 立夏 |
| 5月第2日曜日 | 母の日 |
| 5月15日 | 葵祭り |
| 5月17日 | 三社祭 |
| 5月21日 | 小満 |
八十八夜
立春より数えて88日めである八十八夜。天気模様がよくなり、米や野菜を育てるのにピッタリな時期になります。さらに、やわらかく質が高い茶葉が採れる時期でもあって、八十八夜に摘み取られた茶葉は、末広がりの「八」が重なる縁起物と言われています。
端午の節句
季節の変わり目とされる五節句のひとつで、菖蒲(しょうぶ)で邪気を払うといわれるもの、さまざまな厄除けの行事が行われていました。鎌倉時代に人ると、「菖蒲」と「尚武(式道を重んじること)」を掛けて、男の子の節句ということで祝われるようになりました。
現代にあっては「こどもの日」ということで、男女問わず子どもの健やかな成長を祈願します。男の子のいる家庭では、こいのぼりを立て、五月人形を飾るのが通例です。
菖蒲湯
端午の節句においては、子どもの無病息災を望んで、菖蒲湯で沐浴を行うのが昔からの風習になります。さわやかな香りのする菖蒲は効能にも優れ、抗菌作用があるため風邪予防にもなるので、血行を促進して疲労回復を良くしたり、腰痛や神経痛を穏やかにしたりする働きも見られるのです。
五月人形
江戸時代に、武家が鎧兜の人形を飾ったことが、始まりと言われています。鎧兜というのは命を守る象徴でありながら、男の子を事故や災害から守るという意味も込められているというわけです。
一夜飾りは避け、4月半ばくらいの大安や友引に飾りましょう。片づけは端午の節句が済んだ後の、天気のよい日を選んで片づけるとよいです。男の子のお守りということで、一年を通して飾っておいても問題ありません。三段飾りが基本ですが、家のスペースの関係で、小型の平飾りに人気が集まっています。
こいのぼり
滝をのぼる鯉と同じ様に、たくましく育つことを希望してとの願いが込められたこいのぼりは、江戸時代の庶民の間で広がっていきました。上から順に、矢車(やぐるま)、吹き流し、真鯉(まごい)、緋鯉(ひごい)子鯉(こごい)を飾ります。
柏餅とちまき
端午の節句の祝い菓子は柏餅です。新芽が出ることによって古い葉が落ちる柏は家系が絶えない縁起のよい木とされていて、子孫繁栄をお祈りして柚餅を食べるのが通例となるのです。笹や竹の皮で餅米などを巻いたちまきは、関西地方では一般的と言えます。
母の日
日頃の感謝の気持ちを込めて、母親には赤いカーネーションやプレゼントを贈ります。アメリカ人女性が母親の命日ともなると白いカーネーションを飾ったということが始まりであるとのことです。