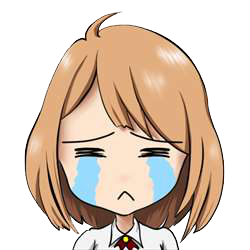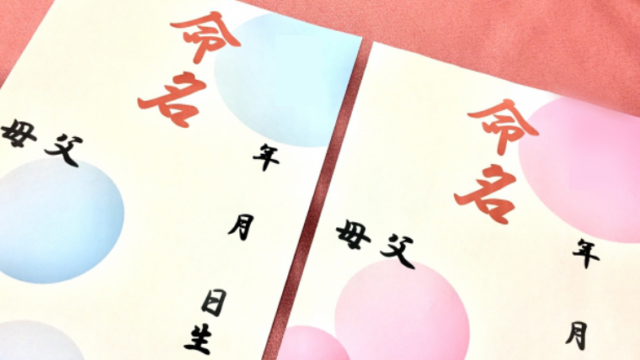料亭での懐石料理となるとマナーが難しそうで敷居が高く気後れしてしまいます。
今後、料亭での会食の予定がある方もない方も、懐石料理のポイントを押さえておけばいざというときに安心ですね。
日本人ならばスマートに覚えておきたい、懐石料理の心構えを解説します。
知っておくと懐石料理を美味しくいただける
誰に奢ってもらえるんですか?
日本科理を象徴する「かいせき」料理。読みは変わらなくとも、二通りの書き表されています。
「会席料理」は宴席で、主体にしてお酒を楽しむという目的で出される料理。対する「懐石料理」の原点はお茶会の席で濃茶を味わう前の空腹を抑えることを考慮して提供される、やや軽い食事となっています。
近年では本来の役目をあえて茶懐石と呼称し、料亭などで提供されるものと区別したりします。
料理屋で出される懐石料理に関して簡単に解説しましょう。
店それぞれで献立は異なってきますが、原則的には先付(突き出し、お通し)飯(お凌ぎ)、吸い物(箸洗い)向付(お造り)八寸(山海の幸の肴)焼き物(季節の魚)煮物椀(季節の野菜の炊きムロわせ)、飯と汁物、香の物、菓子で構成されています。
献立の呼び名と内容を知っておけば、一皿ずついただくので難しいことはありません。
季節の食材と板前の職人技を目と舌で楽しみながら、順番にいただいてください。
料理がすべて一緒に並べられている場合は、献立の順に沿って食べるとスマートです。
マナーも大事ですが、熱いものは熱いうちに冷たいものは冷たいうちにいただく、これが一番の鉄則です。
ふた付きのお椀はどう扱う?
「ふた付きお椀」が出されたときに、扱いに困りがちなのが、取ったふたをどうすれば良いか?また、どこに置けばよいのか?
正しくは裏返して右に置くのです。
裏返す際も、いったん器の上でふたを縦にして、ふたの裏側に付いた水滴を器の中に戻しましょう。
食べ終えたらお椀に戻しましょう。
知っていて損はない抹茶のいただき方
関西地方では煎茶を出す代わりに、抹茶で来客をもてなすことがよくあります。
抹茶のいただき方を知っていれば、人前でぎこちなく抹茶ドギマギしなくて済みます。
先ずはお菓子をいただきます。
茶碗を両手で軽く頭の上にささげてから、正面に口を付けないように茶碗を時計回りに二度回します。
薄茶は何口で飲んでも大丈夫です。
口を付けた部分を指先で拭き、反時計回りに茶碗を二度回して正面を戻すのが作法となります。
まとめ
基本は会食を共にする相手との楽しい時間が大切です。
あまり緊張しすぎてしまうと、せっかくおいしい懐石料理を味わえないなんてことになります。
最低限のマナーを守って、相手にとって不快な会食にならないように、その場を楽しく過ごすことが一番ですね。