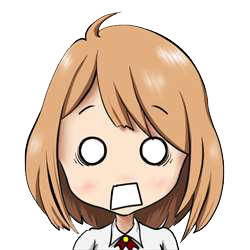臨終を迎えるとその後からさまざまな手続きが始まります。
落ち着いて対応するためには、順序を確認しておくことで、手際よく進められます。
そのためには事前に流れを把握しておくことをおすすめします。
今回は臨終後からの流れをご紹介します。
死亡に関する手続きや順序がわからない
■ なにをしていいのかわからない
■ 手続きはどんなことがあるの?
■ 順序はどうなの?
手続きのすべては死亡診断書からはじまる

臨終から葬儀をおこなうまでにはいくつかの手続きが必要になります。
死亡に立ち会った医師から死亡診断書を書いてもらいます。
病院または医師が死亡診断書を用意してくれるます。
交通事故や変死など病死以外で亡くなった場合は警察に連絡をおこない、警察医や監察医が検視をします。
検視が終了したら、死亡検案書が交付されます。
死亡診断書をもらったら、市区町村の役所に提出し、生命保険、遺族年金の請求、相続税を申告するときにも必要となります。
事前に必要な枚数を確認しておくことで手続きが早く進みます。
死亡届を提出する時期はいつ?

死亡届は死亡してから一週間以内に届け出ることが法律で定められています。
とはいえ、火葬のときには死体火葬許可書の取得に死亡届が必要になるので、死亡の当日もしくは翌日には役所へ提出することがほとんどです。
死亡後の手続きの順序
死亡当日の手続き
医師から死亡届をもらう
・病院で死亡が確認された場合は臨終に立ち会った医師から死亡届をもらう
・自宅で死亡が確認された場合は死亡を確認した医師から死亡届をもらう
・事故死、変死などの場合は警察に連絡して、検視してから「死体検案書」が交付されます。また、病院に運ばれて24時間以上経過後に死亡した場合には医師に「死亡診断書」をもらう。
死亡の当日および翌日の手続き
死亡届を提出する。
提出先は死亡した方の本籍地または届出人の現住所、死亡した場所のいずれかの市区町村役所の戸籍係に提出する。
提出が可能な人は?
1.同居の親族
2.親族以外の同居人
3.家主・地主・家屋管理人・土地管理人
4.同居していない親族
5.後見人・保佐人・補助人・任意後見人
「死体火葬許可証申請書」を提出する。
「死亡届」提出後に戸籍係に「死体火葬許可証申請書」を提出して、「死体火葬許可証」を交付してもらう。
火葬時の手続き
死体火葬許可証を提出する
火葬場に提出します。
火葬が終わったら、証印をおしてもらって返却となります。
証印を押してもらったら「埋葬許可証」として、埋葬、納骨時に提出となるので保管しておきます。
まとめ
死亡から火葬が終わるまでの順序をご紹介しましたが、その時になるとどうしても、手続きやその他の準備などに追われてしまします。
精神的にも体力的にも大変になりますので、事前に流れを理解しておくことで、気持ちにゆとりをもって対応できます。